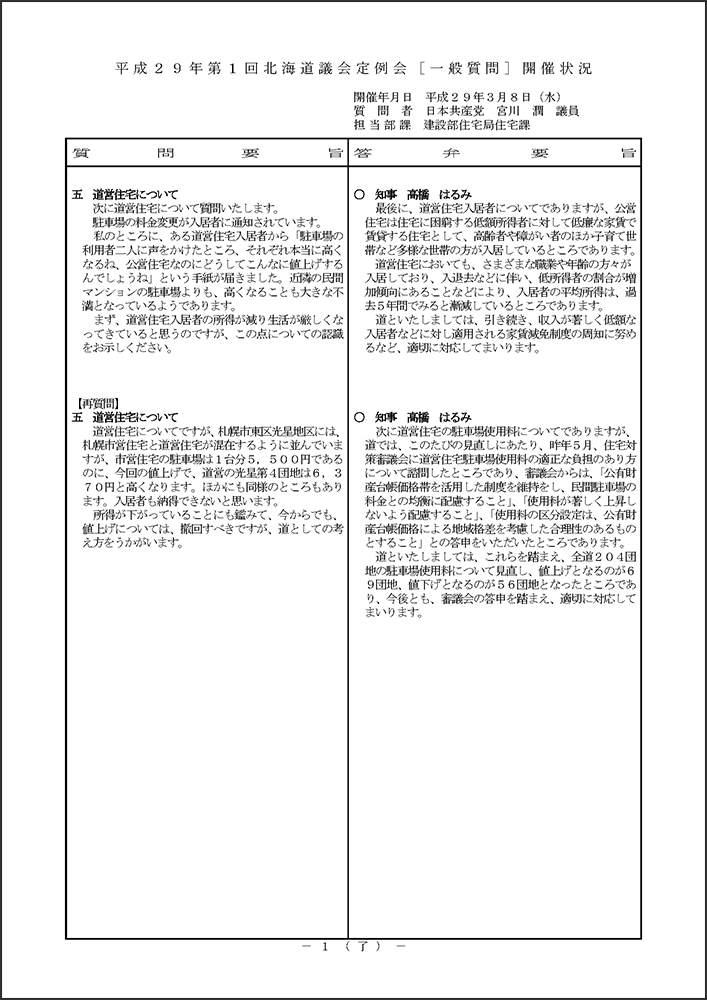【2017年02月23日保健福祉委員会 報告事項4 国民健康保険法に基づく国保事業費納付金の算定に関する報告聴取の件】

一、 国民健康保険の都道府県化について
(一) 国保加入者の状況について
これまでの市町村国保の場合、療養給付費を、保険料と国庫負担および市町村独自の一般会計からの繰り入れで賄い、加入世帯の所得に応じて保険料を賦課することとされてきた。
収納率は、85%にも満たないところがあるなど、保険料負担の重さを物語っていると考えます。
とくに、北海道の場合、第一次産業が国保財政を支える大きな役割をはたしてきました。
国保加入者の職業についての全国調査ですが、農林水産業 従事者は、1965年度には42.1%いましたが、2002年度にはわずか4.9%と激減しています。
また、国保を支えるうえで、第一次産業同様に大きな役割を果たしてきた自営業者は1965年度には25.4%をしめていましたが、2002年度には17.3%へと減少しています。
これらのことから、国保加入者で、比較的所得の多い人は激減しているということであります。
一方、国保加入者で無職の方は、1965年度には6.6%だけでしたが、2002年度には51.0%に増加しています。
国保加入者の所得は大きく下がっていると思いますが、このてんについてどう掌握されているのか、うかがいます。
一、 国民健康保険の都道府県化について
(二)国保加入者の所得と保険料の関係について
札幌市の国保加入者の所得は、1992年度には279万円でしたが、2012年度には95万円と、20年間で約3分の1に激減しています。
国民健康保険加入者の平均所得は、毎年、下がっているのです。
しかし、平均国保料は、上がったり、同じ金額維持するなど、所得が下がっていることにかんがみて、負担は強化され続けていると思うのですが、いかがか、ご見解をうかがいます。
一、 国民健康保険の都道府県化について
(二) 国保加入者の所得と保険料の関係について
再質問か?
国保加入者の所得が下がるのは、農林漁業従事者と、自営業者が減り、加入者の中で無職の方の割合が増えていくという構造的問題です。
ここに歯止めをかけられないのに、保険料だけは下げないので、負担が重くなり続けているのです。
たとえば、札幌市の年金が年間200万円の世帯の国民健康保険料は、1992年度には、47,000円でした。同じ年金200万円でも、2013年度には、125,000円へと2.6倍に上がっています。
平均所得が下がっているにもかかわらず、平均保険料を同額で維持させたためです。
国保加入者の負担感は、全体として、重くなっているという認識をお持ちか、あらためて、うかがいます。
一、 国民健康保険の都道府県化について
(三)都道府県化によって、現実の保険料が上がる問題
配布された資料4「国民健康保険法に基づく国保事業費納付金の仮算定について」の2ページ
一、 国民健康保険の都道府県化について
(三)療養費の差について
公的医療制度において、同じ医療を受ける場合には、どこでも同じ価格・医療費だが、地域によって保険料が違うのは不公平だとの俗論が一部にありますが、医療機関の偏在や、健康診断の実施率、地域の生活習慣など、理由は様々と思いますが、地域によって、医療費に差があるのは事実です。
一人あたりの療養費を比較すると、道内でどのような差があるのか、端的にお示しください。
一、 国民健康保険の都道府県化について
(四)一律保険料について
1番高いところで64万5052円、1番低いところで23万5623円と、2.7倍の差になっている。
療養給付費が違えば、保険料が違うのは当然であります。
医療を受ける状況に大きな違いがあり、療養給付費がちがう状況において、全道一律の保険料を導入することには無理がある、合理性がないものと考えるが、いかがか。
一、 国民健康保険の都道府県化について
(五)収納率と納付金の関係について
市町村は、加入者から、徴収します。様々な事情から、払えない人も出てきます。市町村は、住民に身近ですから、払えないなら払えない理由を聞き、滞納分について分割しながら長期間かけて払っていくとか、働くことができなくなって生活保護で最低限の生活になってしまったなど、状況に応じた対応をするはずです。その結果が、収納率に表れます。
市町村で、加入者から徴収をしても、100%にはならない、しかし、市町村から道への納付金は100%納めなくてはならない、その差は、どうやって埋めるべきと考えますか、うかがいます。
一、 国民健康保険の都道府県化について
(六)基金に償還する財源について
市町村が基金から借りた場合、当然返さなくてはなりませんから、どうやって返すか、その財源です。
徴収した保険料の中から、道に支払う財源を作るとすれば、市町村は滞納分も含めて保険料を100%徴収しなくてはならず、不可能です。
基金から借りた分を返す財源について、どのようにして確保すべきと考えていますか、うかがいます。
一、 国民健康保険の都道府県化について
(七)市町村の法定外繰り入れで解消を図るものについて
市町村が独自財源を投入して、国保会計に法定外繰り入れを行っています。
その理由にはいくつかの区分があり、昨年度道内で実績のった法定繰入を順次あげていくと、(1)単年度決算補填のため、(2)累積赤字補てんのため、(3)医療費の増加、(4)公債費・借入金利息、(5)保険料負担緩和を図るため、(6)地方単独の保険料軽減、(7)任意給付に充てるため、(8)保険料減免に充てるため、(9)地方単独事業の医療給付費波及増、(10)保健事業費に充てるため、(11)納税報奨金、(12)基金積み立て、(13)返済金となっています。
道は、「計画的かつ段階的な解消を進めていく法定外繰り入れの範囲などについて、市町村と認識を共有しながら検討」する旨答弁しています。
ただいま、私が列挙した法定外繰り入れの中で、どれとどれを段階的に解消する対象と考えているのか、明らかにしてください。
一、 国民健康保険の都道府県化について
(七)市町村の法定外繰り入れで解消を図るものについて
再質問
「都道府県国民健康保険遠泳方針策定要領」によれば、「決算補填を目的とした」法定外繰り入れについて「解消または削減すべき」としています。
ただいまの答弁で「(3)医療費の増加、(4)公債費・借入金利息、(5)保険料負担緩和を図るため、(6)地方単独の保険料軽減、(7)任意給付に充てるため」も解消の対象と考えているとのことですが、私は、これらが「決算補填を目的とした」繰り入れとは考えられません。
しかも、本道の市町村すべての繰入金の合計123億円のうち、保険料の負担緩和を図るためが、58%、71億円を占めています。
一、 国民健康保険の都道府県化について
(七)市町村の法定外繰り入れについて
再質問
(八)納付金と保険料の関係について
柔軟で親切な保険料徴収を行うことについて
滞納があっても、それを埋めるだけの高い保険料を賦課することで、道への納付金を納めるということになると、最初に申しあげたように、もともと高い保険料がなおさら高くなり、加入者の負担感はいっそう重いものになります。そのことで、滞納者が増えることもあると思います。
北海道が市町村を叱咤し、度を超えた厳しい徴収へ駆り立てるようなことはあってはならないし、差し押さえ件数を競い合って増やすようなことがあってもなりません。
徴収事務に当たっては加入者の事情をよく聞き、柔軟で親切な対応に徹するように、道として、市町村に働きかけるべきと考えますが、いかがか、部長の見解をうかがいます。